所属学生の声
小関研究室 修士課程1年生(電気電子工学科2023年度卒)

若本裕介さんは理科I類から電気電子工学科に進学し,その後,半導体分野を専門とする研究者になることを志して中野種村前田研に配属されました.卒業研究では,窒化ガリウムの高電界キャリア輸送特性の解明やトランジスタ試作にも取り組み,優れた成果を挙げ,優秀卒業論文賞および学科長特別賞を受賞されました.現在は小関研究室において,誘導ラマン散乱を用いた半導体結晶・デバイスの物性評価に取り組まれています.
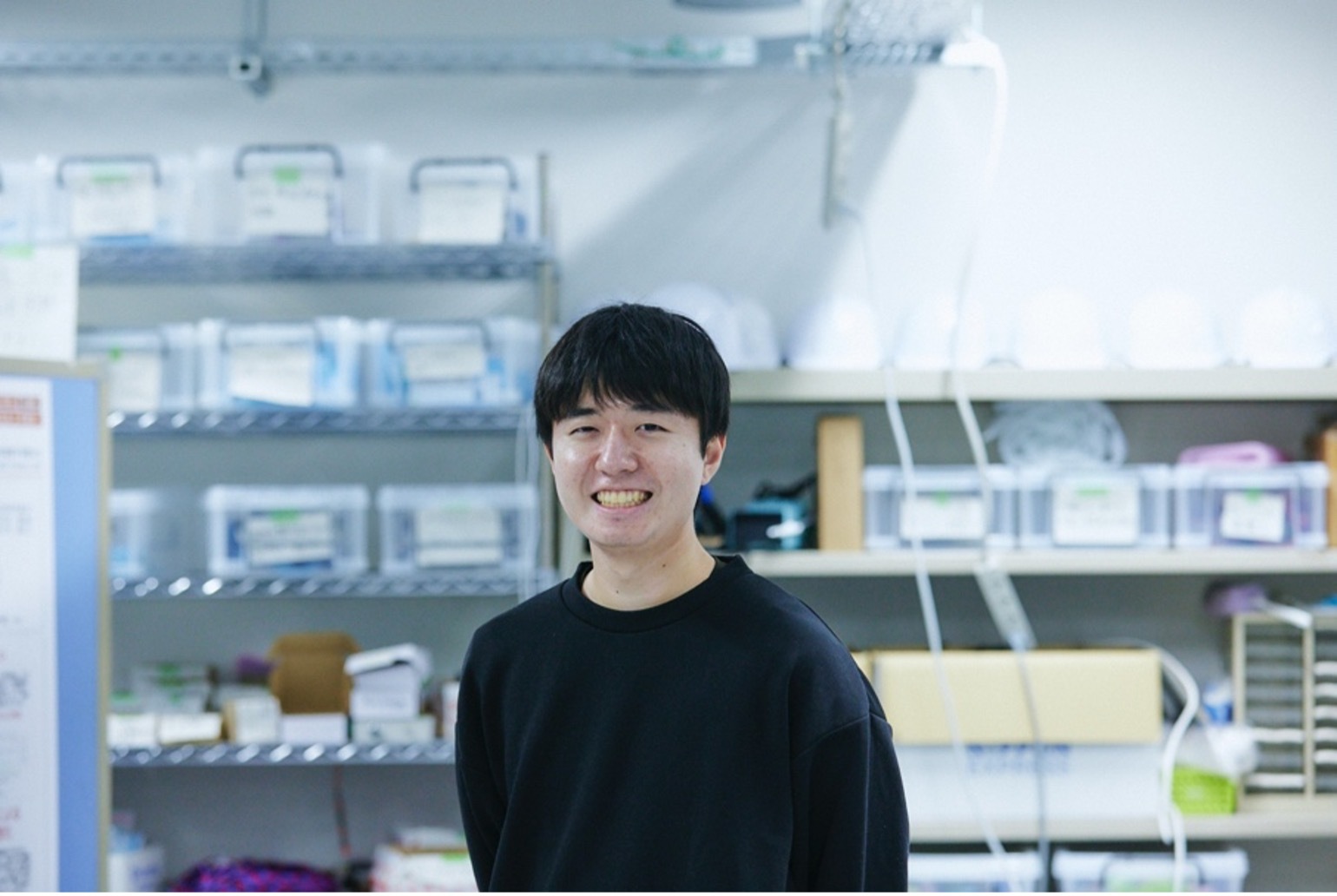
EEICを選んだ理由を教えてください
学んだことが実社会の発展に強く結びつく学科であることが魅力的だと思ったので選びました.EEICでは、AIから半導体,電力エネルギーシステムなど、電気・電子・情報工学の広大な学術・研究分野の基礎を全て学ぶことができます.これらはどれも今後の社会の発展を支える重要分野です.基礎を理解していることは、それら活気あふれる産業へ参入障壁を小さくさせると考え,EEICを選びました.
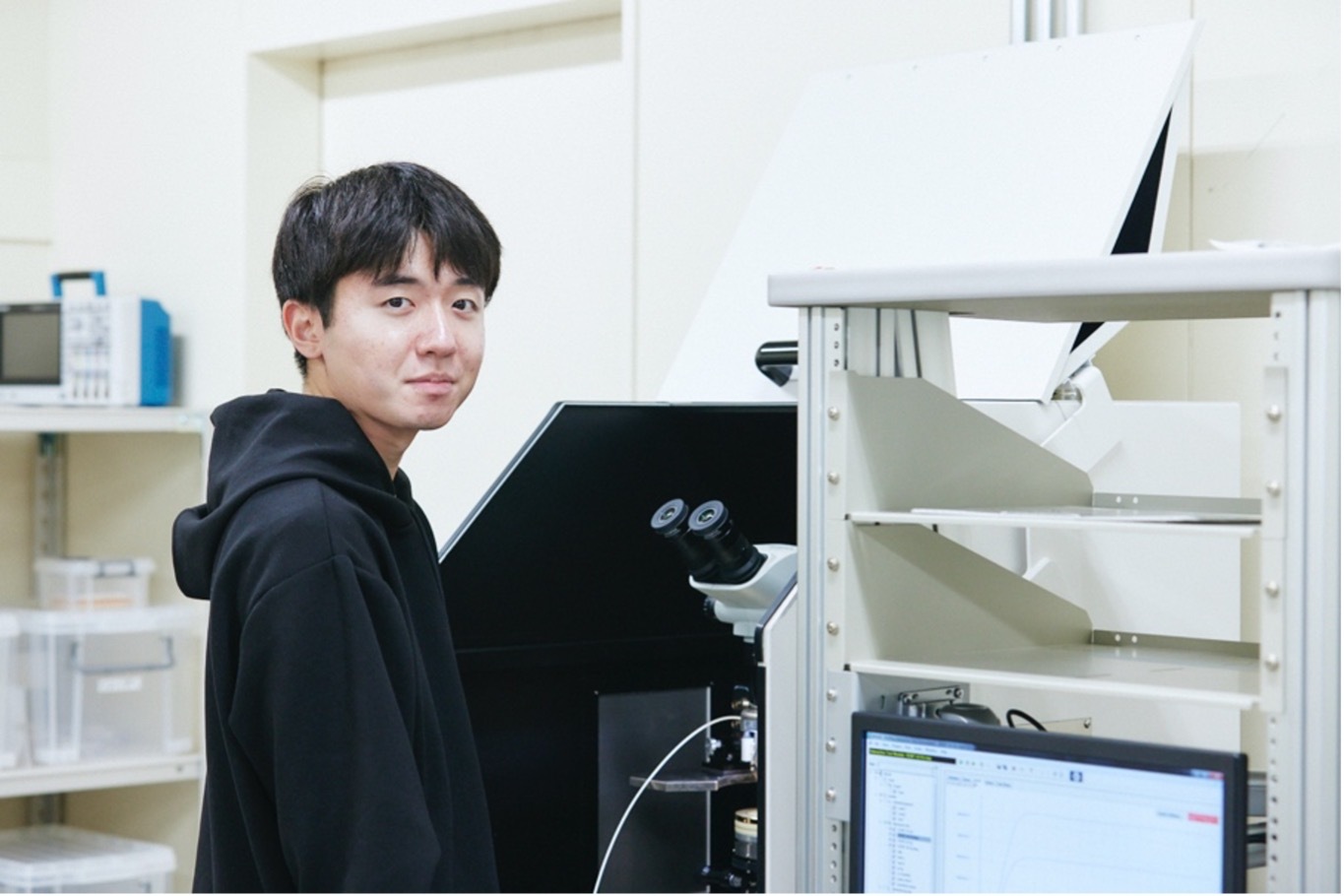
どのような研究をされていますか
半導体デバイスをつくり,評価(測定・解析)をして,半導体の物性を解明する研究をしています.半導体デバイスは、浅野キャンパスにある武田先端知クリーンルームで作製しています.卒業論文では前田研究室に所属し、クリーンルームの先端の半導体プロセス装置をふんだんに使用して,小型充電器に搭載されていることで有名な窒化ガリウム(GaN)のトランジスタを自分の手で作製し,その評価を行いました.今思えば、東京大学でGaNトランジスタを作製した実績はこれまでなく、技術やノウハウをゼロから確立することから取り組むチャレンジングな研究テーマでした.先生や共同研究者の指導の下,粘り強くデバイス作製に取り組み,作製が終わって最初に測定する際は,上手く動作するかドキドキでしたが,理想的な特性が見え,それまでの研究の苦労がすべて報われた気持ちを味わえました.
これらの研究成果は,卒論発表において優秀卒業論文賞・学科長特別賞を受賞したほか,国内学会で発表して奨励賞を受賞しました.また,修士進学後も作製したデバイスの測定を継続して進め,得られた成果を窒化物半導体分野で最大規模の国際会議IWN 2024に投稿したところ,無事採択され,英語で口頭発表を行いました.普段論文で名前を見る海外の研究者からも発表後に質問を受け,議論することができ,大変貴重な体験をすることができました(学会の合間にハワイを観光することができました).現在は学術論文執筆をしております.
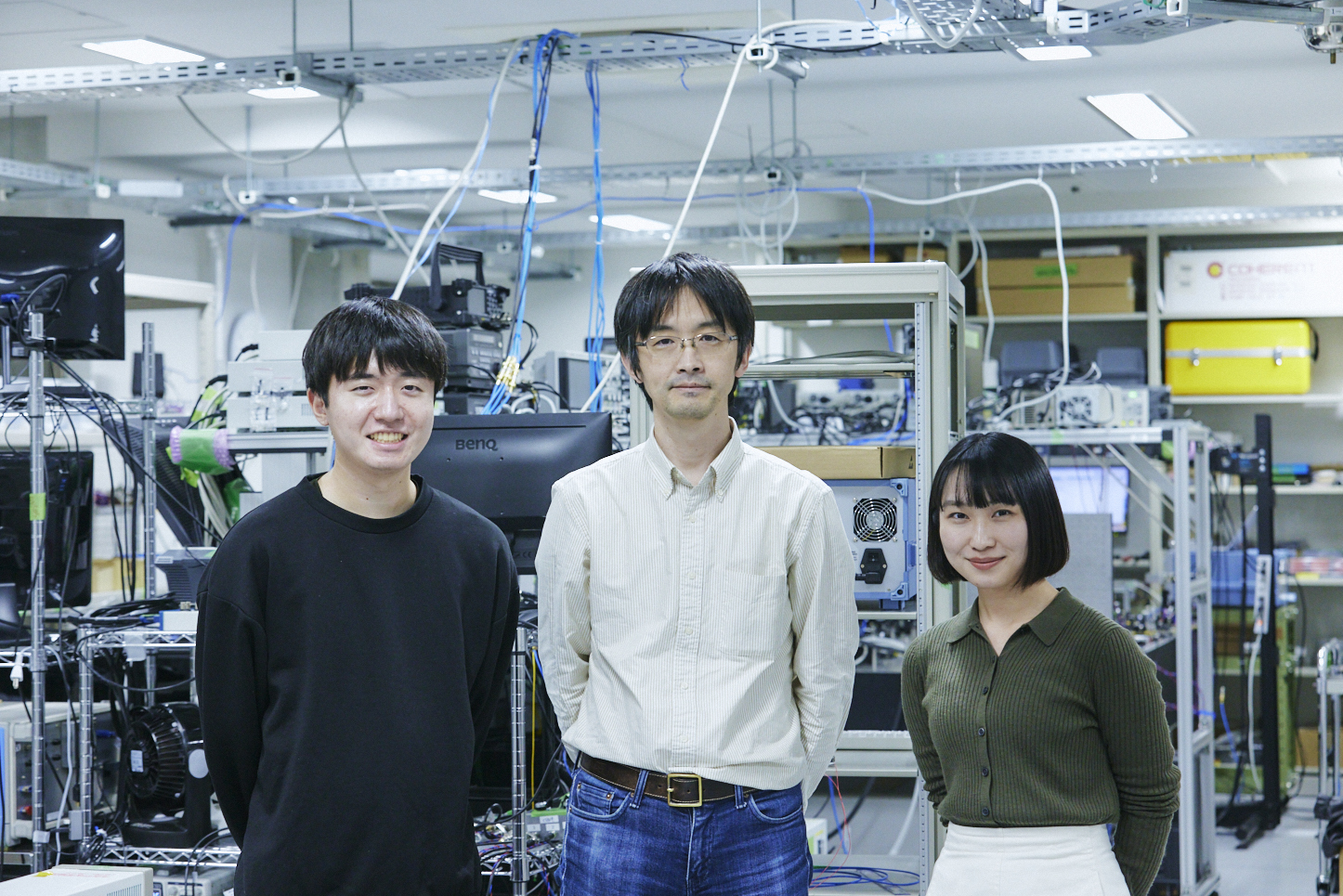
修士研究では小関研究室に所属し,光学の知識を駆使して格子の振動(ラマン散乱)をイメージングし半導体物性を見る研究を行っています.光と半導体の知識を融合させて新しいことを試みるテーマなので大変ではございますが,光・半導体の基礎をともにEEICで学んでいるので楽しんで研究することができています.小関先生・前田先生の両先生の指導の下,分野の融合・境界的な研究を開拓できていると感じており,非常に面白いと感じています.
EEICは忙しいでしょうか
はっきり言って忙しいです.特に,2Aセメスター,3Sセメスターは,高校の授業と同等もしくはそれ以上の時間を取られて大変でした.しかし,その分電気系の基礎知識はしっかりと身につき,中身のある充実した学習をすることができます.今の研究においても,この時期でみっちり叩き込まれたことを使っており,しっかり勉強してよかったと思っています.
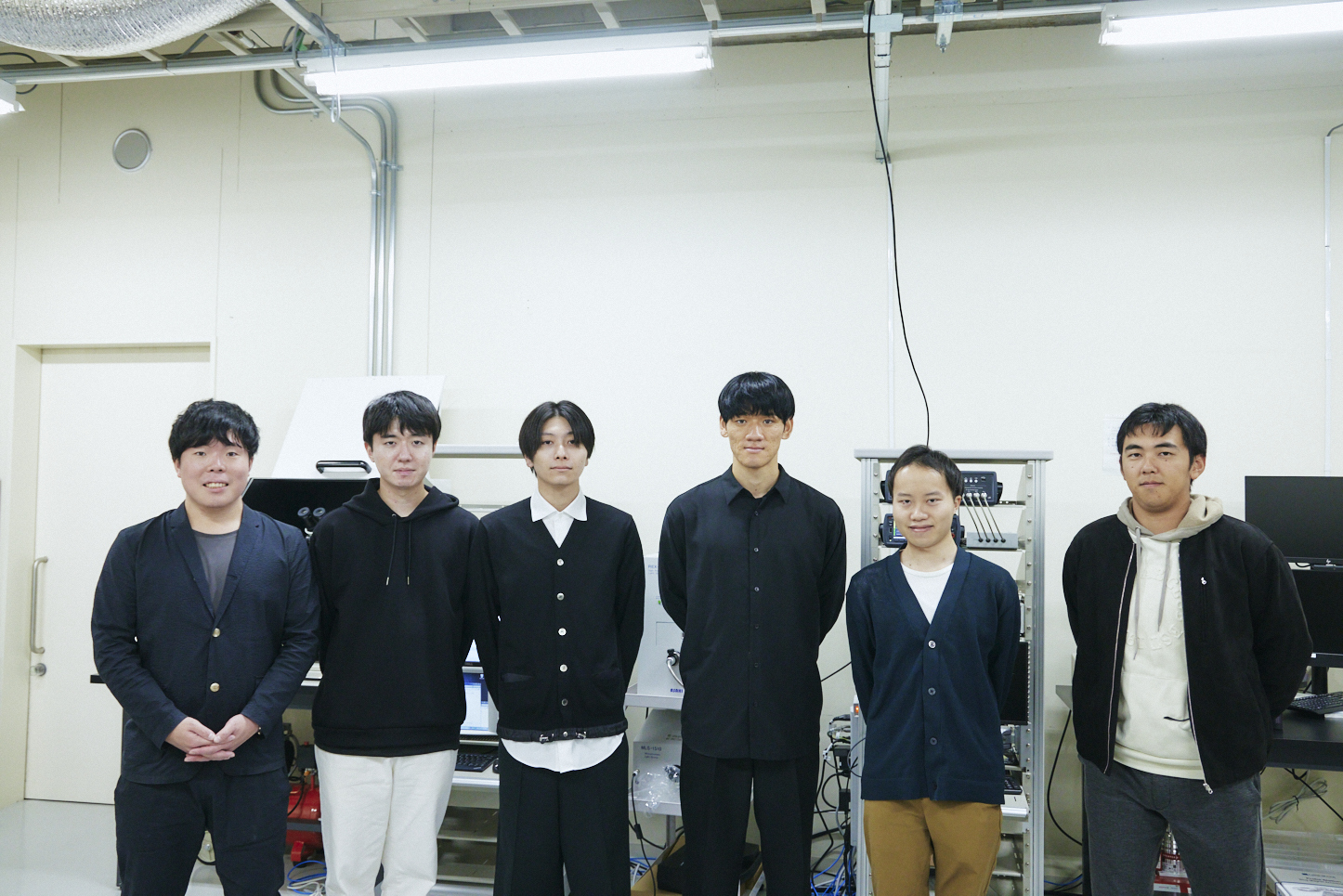
修士卒業後の進路
博士課程進学を志しております.研究をやるなら中途半端にやらずにしっかりやりきりたいという思いで進学するつもりです.博士といえば,経済的に不安・就職難というイメージがあるかもしれませんが,電気系分野では全くそういうことはないと思います.現在は,博士学生に対して18万円以上の奨励金を給付する経済援助プログラムが多数にあり,博士学生は心置きなく研究に没頭することができます(私もヒロセ財団の研究者育成プログラムに採択されており,修士学生ですが,金銭的サポートを受けながら研究に取り組めています.ありがとうございます).私の周囲では修士卒の方々が一度就職しながらも結局博士課程に進学するケースもよく見かけ,博士課程に進学することが全く珍しいものではなくなったと感じております.

EEICを目指すB1, B2へのメッセージ
EEICは楽な学科であるとは思いませんが,充実した学生生活を送ることのできる良い学科だと思っております.仲間とともに同じことを考え,議論する日々はとても楽しかったです.皆様もぜひEEICの生活を楽しんでいただければと思います.